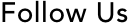【magazine】スペシャルインタビュー2020 第一回「デザイン・ラウンジと津村耕佑」
武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ(以下、デザイン・ラウンジ)は、2020年12月に東京ミッドタウン・デザインハブ内の拠点を閉室し、その機能を市ヶ谷キャンパスへ移行する。この機に、これまでデザイン・ラウンジにご関係頂いた学内外の方からお話を伺いながら、これまでの研究・活動を振り返り検証を行う、デザイン・ラウンジ オンライン企画「スペシャルインタビュー2020」の第一弾。
今回は、デザイン・ラウンジの空間デザインをご担当頂いた津村耕佑先生(空間演出デザイン学科 教授)。開室当時の構想や、アーティストとして観測した六本木という街のアート・デザインの変化を伺い、デザイン・ラウンジのこれまでの役割やこれからの活動を考える。

《公開講座「Explore the Design」第1回》(2015年)
■デザイン・ラウンジの成り立ちについて
――デザイン・ラウンジの開室は2012年4月でしたが、開室準備段階での構想はどういうものだったのでしょうか?
六本木という街は、キャンパスがある鷹の台とは違う要素を持っているので、「ムサビの情報を鷹の台以外でも得ることができる」「都心に出た若者・学生が、気軽に立ち寄ることができる」「学生以外、一般の方にも開放された場を作る」そんな場所として運用しようという話がありました。
思い返せば、デザインという言葉がブームになってきた頃で、デザインが造形的なものだけでなく情報が大事になってくる時代だった。それに、かつては混沌としてアンダーグラウンドな印象のあった六本木が脱皮して、六本木ヒルズや森美術館、新国立美術館や東京ミッドタウンができてアート・デザインが合流してきた後に、さらにアカデミックな要素を取り入れていく動きもあったのかもしれないです。
――なるほど。それで、美術大学によるデザインを情報発信する拠点となっていったのですね。
デザイン・ラウンジのネーミングについてはどうでしょうか。
多様なデザインの姿を見せていくことに意味があったので、デザイン・ラウンジを単なる情報発信のみにカテゴライズしたくないという思いがありました。訪れる人、関係する人達が醸し出す空気感で意味が作られていけばと考えて、「ラウンジ」を使いました。ラウンジという言葉には高級なイメージがあって、たとえば空港のラウンジは「クラス」を表す要素もありますが、そうではなくて「ボイドのもつ自由な空気」に近いものをイメージしていました。
しかし、内装に悩みました。本来、内装とは目的に基づいて設計されるものなので、「そこに集まる人によって変容していく空間」を作るというのは難しかった。考えた末、株式会社E&Y(ファニチャーレーベル)と相談してコンセプトに見合うインテリアを選定して、空間はできるだけ開放的に、フラットにしました。
自由な組み換えが可能な什器の簡素さと機能が重要で、敢えてのラウンジのようなゴージャス感を出さないようにしました。これを、○○風のようなスタイルにはめると人を選んでしまうので、テーブルや椅子、照明が似たようなコンセプトを持つけれど、あえてデザインを統一していません。
オフィススペースとオープンスペースの間のパーテーションも隙間が空いていて、ゆるやかに繋がった日本的な分割方法かもしれません。人の視線で人は行動を意識するので、ラウンジスタッフも存在として自覚的あるということは重要です。隠しすぎることは逆にタブーを感じさせるので、良くないという思いもありました。
――仕事中のスタッフの様子や、トークイベントやワークショップを開催中の様子が常に外から見えるので、日々のライブ感は発信できていたかなと思います。それに、「作られていく空間」というコンセプト通り、デザイン・ラウンジは企画に合わせて緩やかに形が変えられる自由な空間でした。
――デザイン・ラウンジのVI(ビジュアル・アイデンティティ)について、教えてください。
デザイン・ラウンジのVIは、原研哉先生(基礎デザイン学科 教授)が手掛けました。ロゴマークは、丸みを帯びた「D」の形をしていますが、「DなのかOなのか、判別が難しい」という意見もありました。原さんは、「そこがいい。わからないのが、いいじゃん」と。見る人が、それぞれの解釈をしますよね。「O」は文字の形から「広がっている、丸い、繋がる」のようなイメージを持ちますが、「D」はデザインのDであるとすぐイメージできる。そこを曖昧にしておくことで見る人に考えさせるのは、素晴らしいコンセプトだなと思いました。
国旗やピクトグラムは瞬時に理解できないと機能しませんが、デザイン・ラウンジの場合はロゴマークの目的が単なる判別ではないので、多様性というがよく表れていたのです。
あとは、デザイン・ラウンジの壁一面をホワイトマグネットボードにしました。工事は大変だったようですが・・。プロジェクターによる投影ができるだけでなく、何か書くときに位置の制約がない状態で書けるのが良いですね。人類が壁画を描き始めた時のようなイメージです。
■津村先生と六本木のアート・デザインについて
――六本木の街とアート・デザインの関係についてお伺いします。津村先生は、デザイン・ラウンジ企画で六本木アートナイトに出展頂いただけでなく、初回である2009年開催の六本木アートナイトにも出展されていました。
初回から11年が経ちましたが、六本木の街におけるアート・デザインの変化で感じていることはありますか?
当時の出展アーティストは、とても多様でした。警察による取り締まりが発生することもありましたが、だからここそ解放の役割を担うアートという空気感もありました。面白そうだったので、ゆるい感じで初回の六本木アートナイトに参加しました。六本木の街は、クラブや飲食店はたくさんあるけれど、オープンに集まるような「お祭り」の場がなかったんですよね。非日常的刺激がある街だけど、コアなお店は路地や地下に隠れているのです。それも文化的な特徴と言えますが、人々がビジネス抜きで解放的なアートシーンに出会う機会が少なかった印象です。
そこで、六本木アートナイトがその役割になっているようでした。言葉的にはアートを使っていますが、どちらかというとお祭りだろうなと。「ハレとケ」で言えば「ハレ」にあたる、特別な時間。夜を舞台に魑魅魍魎が現れて、明け方になって帰って行くみたいなイメージです。六本木アートナイトに限らず最近では多くのアートイベントが行われ、それに伴い地域とのトラブルも心配され監視の目も厳しくなっていますね。
――六本木アートナイト2017で出展頂いた「夢夢神社」は夜間の設営で、津村先生だけでなく当時の空間演出デザイン学科の研究室スタッフの皆さんにも大変お世話になりました。
その前の年は、空間演出デザイン学科の学生によるファッションショーMAU COLLECTION「IMIN」で出展頂きましたね。
こういったプロジェクトを学生たちに話す時は、伝え方を工夫します。課題の様に強制感を含めて伝えると学生たちのテンションが落ちるので、自主性に委ねる必要があるんです。「いすみ市の漁港で行われたファッションショー」のときに学生としてプロジェクト参加した卒業生がデザイン・ラウンジでスタッフとして現在働いていますが、彼女の代はそのチャンスを逃す事なく上手くハマったのではないかなと思います。そして、こういうことが毎年行われる訳では無いし、学生のモチベーションや学年の雰囲気もあるので一期一会の体験ですね。
 《MAU COLLECTION 「IMIN」~六本木アートナイト2016~》(2016年)
《MAU COLLECTION 「IMIN」~六本木アートナイト2016~》(2016年)
――「MAU COLLECTION」は、空間演出デザイン学科で初めての社会連携プロジェクトでした。オープンキャンパスでの公演をきっかけに、「六本木アートナイトと千葉県いすみ市の大原漁港、二つの機会があるけどやってみない?」というお話から始まった記憶があります。
鷹の台キャンパスから始まって港区六本木、千葉県いすみ市にてファッションショーを開催しましたが、それぞれの機会におけるメリットや、出来上がってきた作品の違いはありましたか?
まず、それぞれの場の雰囲気が違いますよね。本来の「MAU COLLECTION」は大学でのオープンキャンパスで開催するものなので、学生にとって慣れたホームで開催するんです。だから、やりやすいんですよ。しかし、そのままのパッケージで外に出ると全部が変わって見え出します。「あれ?こんなはずじゃなかったのに。」と、自分の作品に対する見方が変わります。
六本木であれ千葉であれ、どこでもいいかもしれませんが、違うところに自分の作品を置いてみないと、客観的に作品を見ることができません。学内での調和に安住せず外の風に晒したほうが作品もより良いものになっていきます。
 《MAU COLLECTION 2016「DEN」 いす×むさ》(2016年)
《MAU COLLECTION 2016「DEN」 いす×むさ》(2016年)
——デザイン・ラウンジでは対外的なプロジェクトも多く実施しましたが、鷹の台だけでは出来ない活動を意識していたので、その意味では間違っていなかったなと思いました。
2020年の六本木アートナイトは、感染症予防のため中止になってしまいました・・やむを得ないことですが、残念です。
この状況を逆手に取って社会全体で価値観の変換ができるかどうかという時期ですね。以前と同じ状況に戻そうと努力しても7割くらいしか戻りませんでしたというネガティブな感覚に囚われるより0からマインドセットを変えたほうがいいんじゃないかと思っています。
■六本木から市ヶ谷へ、デザイン・ラウンジの機能を移行することについて
——2020年12月に東京ミッドタウン・デザインハブ内の拠点を閉室し、その機能を市ヶ谷キャンパスへ移行します。
六本木での情報発信拠点としての期間を経て、市ヶ谷は実際に社会を学びのフィールドとして捉えるイメージですが、今後の活動についてはどうでしょうか。
六本木にも地域・場所ならではの特性があるように、市ヶ谷にも場所の特性があるので、六本木にあるデザイン・ラウンジの空気感をそのまま移すというのは難しそうですね。ですが、市ヶ谷キャンパスには造形学部とは異なる目標をもつ学生もいると思うので教授たちも初めて向き合うシステムの活用に止まらず開発までしていく様な事が行われるといいですね。コンピューターが出始めた頃の、何に使うのか分からないけどとにかく自分から始めようといったイメージです。
それに、走っている時には姿かたちが分からないものなので、のちに市ヶ谷と鷹の台と六本木を比較してみると、何かが見えてくると思います。
――そうですね。この先の2029年には武蔵野美術大学100周年を迎えますし、変化する社会の中で美術大学が何をするべきなのか考える良い機会なのかもしれません。
津村先生、本日はありがとうございました。

津村耕佑 ファッションデザイナー
1959年 生まれ
2008年度 着任
「FINALHOME」ディレクター。究極の家は服であるという考えを具現化した都市型サバイバルウエアー「FINALHOME」を考察する。パリコレクション、ロンドンコレクション、東京コレクションなどのファッションシーンを通過しながら、デザインやアート、建築の分野を越境した活動を展開。第52回装苑賞、第12回毎日ファッション大賞新人賞、第3回織部賞を受賞。
(文=武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ)
【スペシャルインタビュー2020】
第二回「デザイン・ラウンジと美術大学の社会連携」
https://ichiemu.musabi.ac.jp/2020/07/14085
第三回「デザイン・ラウンジと学生ワークショップ」
https://ichiemu.musabi.ac.jp/2020/08/14148
第四回「デザイン・ラウンジの成り立ち」
https://ichiemu.musabi.ac.jp/2020/08/14254
第五回「デザイン・ラウンジとこれからの集まる場」
https://ichiemu.musabi.ac.jp/2020/09/14424
第六回「東京ミッドタウン・デザインハブとデザイン・ラウンジ」
https://ichiemu.musabi.ac.jp/2020/09/14544
第七回「東京ミッドタウンとデザイン・ラウンジ」
https://ichiemu.musabi.ac.jp/2020/10/14640